
今さら聞けない あんな質問、こんな疑問を、RSが代わりに伺ってきました。
今回は【メモリーカード/PCカード用コネクタ編】です。
<取材協力:取材協力:ヒロセ電機株式会社>
PC/デジカメ/ケータイ
■ 種類と変遷
- ──── 様々な機器に色々な種類のICカードが使われていて間違えてしまいそうです。
最近ではSuicaやICOCAに代表される非接触型のカードやICを組み込んだ銀行カードなどを指してICカードと称する例も多いのですが、ここでは機器に差し込んで使うタイプのものについてお話しします。携帯電話やデジタルカメラをはじめ、カードを併用する小型電子機器が増えています。身の回りで使う機器だけでなく、電子計測器や工作機械などの組み込み機器・産業機器などにも盛んに利用されるようになりました。市場には用途に応じて様々な種類のカードが出回っていますが、各カードはそれぞれが規格に基づいたものであり、カードもコネクタも電子回路インタフェースも安心して利用できます。 機器挿入型のカードはノートパソコンの機能拡張などに使われる「PCカード」が普及のきっかけだったと言って良いでしょう<図1a>。例えば無線LANやPHS接続のカードを使っている方も多いはずです。PCカードは俗にPCMCIA(注1)などとも呼ばれてきましたが、現行のPCカードは、JEIDA(注2)Ver.3/PC Card Standardで規定されています。また、従来は16ビットバスによる転送でしたが、32ビットに拡張して高速化を図った「CardBus」規格対応のものも多くなりました。最近では、より高速なExpressCardも普及しつつあります。
図1:

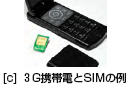
挿入型のカードはその後、フラッシュメモリの実用化に伴って小型の「メモリーカード」として急速に普及したことはご承知の通りです。デジタルカメラや携帯電話のデータ保存メディアとしてコンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDメモリーカード、メモリースティックなど、多数の規格が生まれた背景には、マルチメディアをはじめとするメモリ需要に裏付けられた膨大な市場が見込まれるという事情があります<図1b>。
小型のカードではもうひとつ、携帯電話用SIM[シム]の需要があります。SIM(Subscriber Identity Module Card)は、GSM規格の携帯電話で第二世代から用いられているもので、カードを差し替えるだけで携帯電話の乗り換えができるものです。日本の携帯電話はGSM方式を採らなかったのでSIMは使われなかったのですが、GSMはワールドワイドでのシェアが大きくその数は膨大です。日本では3G(第三世代)携帯から類似の仕組み(現行ではユーザによる差し替えは不可)とカードが組み込まれるようになりました<図1c>。
傾向と対策
■ カードとコネクタのトレンド
- ──── 携帯電話でも写真などのデータを小さなカードに保存するようになりましたね。
-
図2:メモリカードのサイズ比較
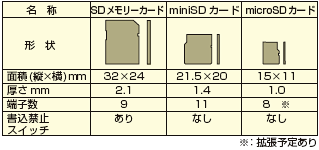
電子機器の小型化と高密度実装に応えるために、カードやカードを接続するコネクタにも小型・薄型化が要求されています。特にメモリーカードでは、デジタルカメラ向けなどで大容量化が進む一方で、携帯電話向けなどでは小型化が進みました。
<図2>はSDメモリーカードについて小型化への変遷を示したものです。当初のSDメモリーカードとmicroSDカードを比較すると面積は約1/5、厚さも半分以下となっています。 同時に対応するコネクタも小型・低背化が進んでいます。ちなみに、多くのアプリケーションではカードを機器本体の側面など外部から抜き差しするようにしているため、カードを押す毎にロック/抜去される「Push-Push方式」のコネクタが多く使用されます。この場合、Push-Pushを実現するメカニカルな部分の大きさがコネクタサイズを左右します。Push-Pushの仕組みは、コイルバネとハート型のカム機構などで構成されますが、これらを如何に小さく実現するかがコネクタメーカの腕の見せ所です。例えば、<図3>に示した商品では15.95×13.85mmで厚さ1.68mmを実現しています。
図3:microSDカード用のコネクタ例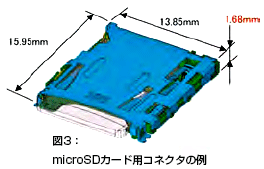
いっぽう、小型化を目指してカードを立ち上げて引き抜く「ヒンジ」タイプのコネクタも使われるようになってきました<図4>。このタイプではPush-Pushの機構が要らないので機器をより小型にできます。記憶容量が増えた結果、抜き差しの頻度がさほど多くないのであれば、カードを電池ケースの裏側など内部に取り込んでヒンジタイプのコネクタを使えばいいわけです。
図4:ヒンジタイプのロック解除操作と抜去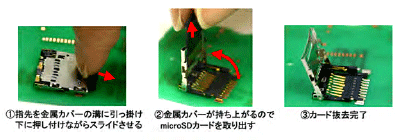
技術の隠し味
■ コネクタの付随技術
- ──── カード用のコネクタには技術的にどんな工夫が込められていますか
メモリーカードなどは一般の消費者が扱うアイテムです。しかも日常的に操作するものではありません。したがってコネクタは、基本機能を優先しつつも、誤挿入などコンシューマの使用状況に対する配慮を盛り込む必要があります。具体的な例としては、カードの方向や表裏を間違えて差し込もうとしても入らないようにするといった配慮が必要になります。microSDなどの小型カードではさらに、カードを引き出す際の排出量を多くして取り出しやすくすると同時に、カードが本体から飛び出して落としてしまう事がないようにストッパーで停止させる機構を盛り込まれています。また、カードサイズや許容差などは規格で定められますが、実際にもかなりの個体差があります。コネクタ側でそれらのバラツキを吸収することが求められるわけです。極小のコネクタでこれらを実現するには多くの技術とノウハウを要します。
ちなみに、コネクタのピン配置など基本的構造はカードの規格に依存するわけですから、規格の動向はカードのユーザだけでなくコネクタメーカにとっても目が離せません。このため、規格の策定に当たってはコネクタメーカも積極的に参画してより使いやすいカード/コネクタを目指しています。
(注1):PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association):PCカードなどの規格を策定している団体図5:コンシューマの使用に対する配慮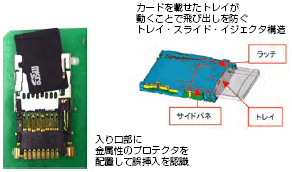
(注2):JEIDA:日本電子工業振興協会、現在の電子情報技術産業協会(JEITA)●本節で採り上げた各商品名は以下に示す各社・各団体の登録商標です Suicaは、東日本旅客鉄道株式会社 ICOCAは、西日本旅客鉄道株式会社 コンパクトフラッシュは米国SanDisk Corporation ExpressCardは、PCMCIA SmartMediaは、(株)東芝 SDメモリーカードは、松下電器産業(株)、米国SanDisk Corporation、(株)東芝 メモリースティックは、ソニー(株) miniSDおよびmicroSDは、SD Card Association
