
今さら聞けない あんな質問、こんな疑問を、RSが代わりに伺ってきました。
今回は【クーリングファン編】です。
<取材協力:山洋電気株式会社 様>
省エネのいっぽうで機器の発熱量は増加傾向
■ ファンの種類と使われ方
- - 機器の発熱をファンで抑えることになったのですが、どこから手を付ければよいのか分かりません。
-

軸流ファン
(筐体全体の換気など)
CPUクーラー
(特定デバイスの冷却)
ブロア
(通風抵抗の大きな装置の冷却など)【図1】:様々なクーリングファンと
用途ファンによる冷却を考える場合、最初の判断事項は、機器全体を冷やすのか、内部の特定の発熱部分を冷やすのか、ということです。機器の内部全体を満遍なく冷やしたい場合は、筐体にクーリングファンを取り付け筐体内部全体を換気します。機器内の特定の部分を冷やしたい場合は、その部分にクーリングファン出口からの空気流を直接あてる工夫をしたり、CPUクーラーを使ったりします。また、内部発熱がそれほど大きくなく、風量はあまり必要ないけれども、空気の流れる空間(通風路)がほとんどないような通風抵抗の大きな装置を冷やす場合にはブロア型のファンも使用されます。
次に、クーリングファンには、大きく分けて、交流電源(100V等の商用電源)で回るACファンと、機器内部で作り出された直流で駆動するDCファンがあり、どちらにするかを決めます。ACファンに用いられるモータには「くまとり(隈取り)型」と「コンデンサ移相型」とがあります。いずれも商用電源をそのまま接続しますが、「くまとり(隈取り)型」の方が効率は悪いもののコスト的に有利です。
DC駆動のファンにはブラシレスモータが使われます。ブラシレスモータは、DCモータの電流切り換えブラシ(電機子)を半導体回路に置き換えたもので、ACファンに比べ低消費電力である、制御しやすいなどのメリットがあります。温度センサを内蔵し温度によって回転速度が変わるものなども多く使われており、最近では装置側からPWM制御によりファンの回転速度を精度よくコントロールできるタイプも増えています。
WEBでの簡単設計も有効
■ 装置冷却設計と機種選定フロー
- - 電気でも機械でもない設計にとまどっています。設計の手順を教えてください。
-
装置冷却設計方法の詳しい説明は、ほかの専門書に譲るとして、ここでは筐体全体を冷やす場合におけるファン選定方法の例を紹介します。おおまかな手順を<図2>に示しました。
まず、対象となる機器の発熱量と装置に許容される温度上昇とから、冷却に必要な風量を計算します。この場合の熱量とは筐体内に熱として放出される電力のことですから、アンプのように出力を持つ機器では、機器の消費電力から出力電力を差し引いた値とみなせます。求めた風量を1.5~2倍した値の最大風量を有するファンを選びます。その際、駆動方法やファンのサイズなどの条件と照合すれば機種を決定できます。これらは自分で必要風量、最大風量を計算して求め、カタログを参照して決めることもできますが、山洋電気ではWEB上で条件やパラメータを入力するだけで条件に適した機種を選定できるツールも用意しています。これを使えば簡単にしかも素早く機種選定できます。
なお、こうした簡易的な方法は、通風路が十分に確保されていることを前提にしていますので、筐体内部の実装密度が高い装置(通風抵抗の大きな装置)などでは、より多くの風量を確保したり、局部冷却を併用したりするといった工夫が必要になります。
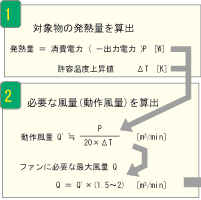
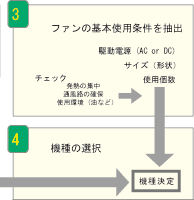 【図2】:機種選定までの流れ
【図2】:機種選定までの流れ
使用環境を考慮すべし
■ 使用環境とファン寿命
- - 寿命とか交換とか考えないといけないですよね。使う環境とかにもよるのでしょうけど。
- 【図3】:ファンの基本使用条件を抽出
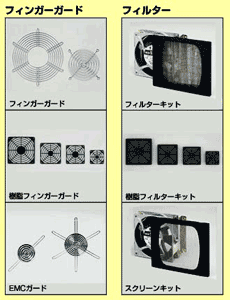
ファンは長時間の高速運転に耐える製品ですが、当然、寿命があります。その寿命は使用環境によって異なりますが、特に温度の影響が大きく、カタログ等で記載される数値には必ず何℃における値、といった表現がされています。もちろん、塵芥の多い環境などで使用すれば寿命は短くはなりますが、大雑把に言って、通常のACファンで25,000時間、DCファンでは40,000時間はあります。さらに長寿命タイプの製品の中には20万時間を達成している特殊な製品もあります。この場合、20年間以上も連続運転できるわけで、機器本体の寿命よりも長いかもしれません。こうなると、ファンの交換は考える必要がありません。なお、FA機器など悪条件下での使用に対しては、防油仕様や防水仕様のファンがあります。
取り付けとオプションの知識
■ 使用上の注意
- - 取り付け場所や取り付け方法で注意する事項はありますか。
-
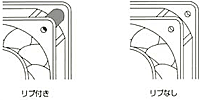
取り付け部分がリブつき構造のものとリブ無しの製品がある
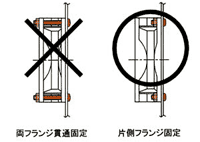
リブの無い製品を長いネジで貫通して固定してはいけない
【図4】:取り付け上の注意露出して取り付ける場合は、安全対策としてフィンガードを使用してください。 また、塵芥対策が必要な場合はフィルターの併用を推奨します。また、ファンを取り付けるとその開口部は、電磁波が自由に行き来できる通り道になるため、電磁ノイズの出入り口が設けられたとも言えます。ファン単体でできる対策はファンの接地やシールドをしっかり採ることですが、装置としての対策も講じる必要があります(<図3>参照)。
実際の取り付け上の注意としては、フランジの取り付け穴にリブの無い製品を、長いネジで貫通して固定することは強度に問題があるので避けてください(<図4>参照)。希にタッピングビスで取り付けようとする例も見受けますが、これもやってはいけません。
